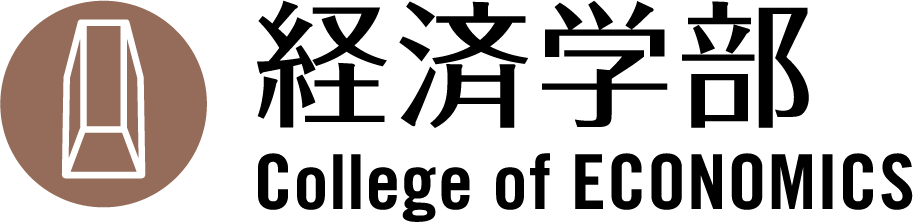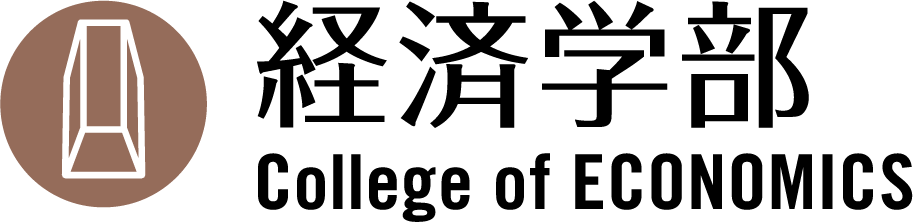経済学部教員コラム vol.112
細谷 早里新約聖書の世界で考えたこと
経済学部で教職課程、グローバル時代の教育を担当している細谷早里です。多文化社会になりつつある日本の教育、多文化共生のための教員養成のあり方について研究しています。
学会参加のため2015年にトルコのエフェソ、2018年にキプロス、そして2024年にはギリシャのテサロニケを訪ねる機会がありました。新約聖書には、伝道のためにパウロがキプロスのパフォスに立ち寄ったこと、紀元53年にエフェソに到着したのち、紀元55年にはテサロニケへ赴いたことが記されています。長らく土砂に埋もれていたエフェソの町は、現在発掘が進んでいます。テサロニケの地では数々の古い教会の遺跡が残っていました。パウロは旅の後、テサロニケの信徒への手紙、エフェソの信徒への手紙を綴っています。長い時を経ても確かに彼の足跡を感じ取ることができました。
パフォスの港町を歩いたとき、砂埃で汚れた自分の足を見て、イエスが弟子たちの足を自ら洗ったという場面を思い出しました。それは互いに仕え合う生き方を示す模範でした。「人になれ 奉仕せよ」という関東学院の建学の精神を思い出しました。
多文化共生は「お互いの違いを認め合い、対等な関係を築きながら、地域社会の構成員として共に生きていくこと」です。その意味を考える時、あらためて建学の精神の普遍的な価値を感じます。教育研究に携わるものとして、その精神を胸に学生と共に学び続けていきたいと思います。