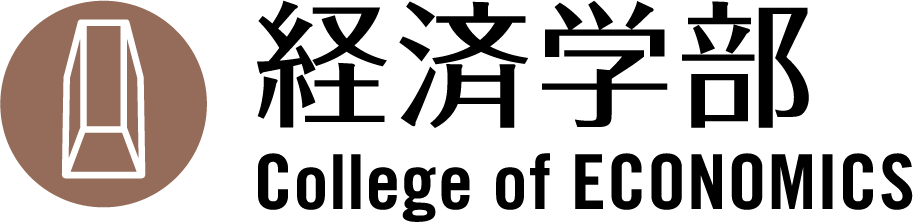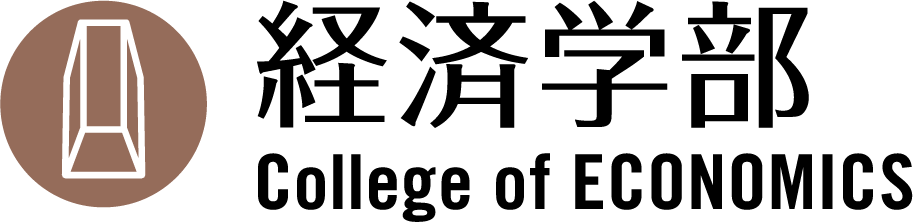経済学部教員コラム vol.46
「経済学の今昔」
こんにちは、本学経済学部で「経済学史」を担当している石井と申します。前にもこのコラムで取り上げた、カール・マルクスの『経済学批判』という著作にもう一度触れたいと思います。
かつて『経済学批判』というと、「人間は、その生活の社会的生産において、一定の、必然的な、かれらの意志から独立した諸関係を、つまりかれらの物質的生産諸力の一定の発展段階に対応する生産諸関係を、とりむすぶ……」(武田隆夫ほか訳『経済学批判』岩波書店, 1956年, 13ページ)という何やら難しい文章ではじまる、史的唯物論とか唯物史観と呼ばれる歴史観が展開されていることでよく知られていました。
人類社会の歴史的発展を推進する力は何か、というときマルクスは、理念や人々のものの考え方の変化が果たす役割を否定するわけではありませんが、それよりも生産力の発展に基礎づけられた、経済的・社会的条件の変化を強調します。人類の社会は原始共産制からはじまって、いくつかの段階を経て資本主義社会に至り、最後には社会主義や共産主義にとって代わられるとマルクスは信じていました。
このマルクスの考えには賛否両論がありましたが、かつては歴史学においても大きな影響力をもっていました。いまではあまり言われなくなりましたので、このコラムを読んでいるみなさんも初めて聞いたという方も多いでしょう。
ところで、経済学というと非常に現代的な学問というイメージがあるのではないでしょうか。かつては経済学の目的について、湖に浮かぶボートにたとえて、経済が沈まぬようバランスをうまくとることと説明した人がいました。まさに現今の経済に焦点が当てられているわけですが、それと比較すると、太古の昔から現代にいたるまでの歴史を考えるなんて、変わっていると思いませんか。
しかしマルクスや彼に先立つ古典派と呼ばれた人々(アダム・スミスなど)が生きた150~200年前の西欧社会は、工業化とともに大きく転換しつつあり、人々にあいだには、社会がどのような方向に変化してゆくのか不安がありました。また現代に比べて統計が充実しておらず、少しでも多くのデータを得るには、歴史を遡らなければならなかったのかもしれません。そういった要因により、これまでの歴史的変化をふまえて将来を見通そうとする観点が生じたのでしょう。いわば長い時間のなかで、船がどこへ流れてゆくのか見定めようとするわけです。

まだ生じていないことを取り扱うのは学問的には限界があるのですが、それでも、歴史をもとに将来を見通そうとする彼らの壮大なものの見方に、何かわくわくするものを感じませんか?