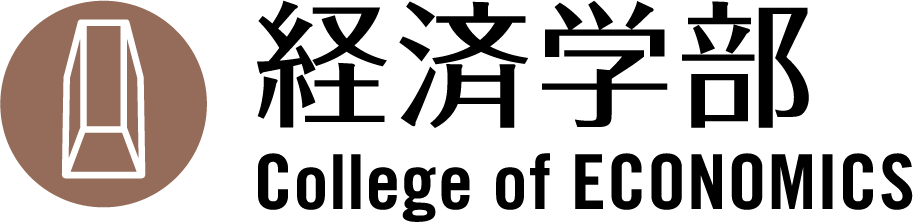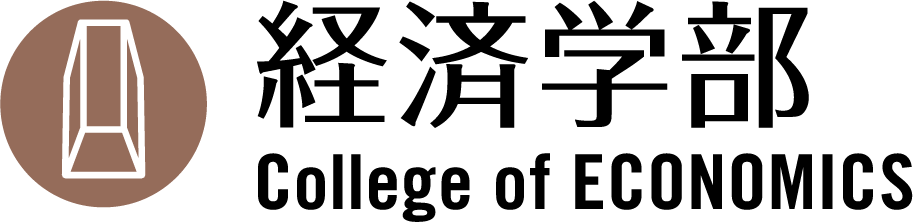経済学部教員コラム vol.57
抵抗権の「否定の否定」
近代政治学の父とされるロックが『統治論』(1690)で人民主権と抵抗権を認めたことはよく知られる。それは、人民の同意にもとづいて政治的社会を設立したとするかぎり、信託権力である政府が圧政を働いた場合に、人民がこれに抵抗する権利をもつというのは、人民主権を保証する根拠として必要だったからである。これは、立憲主義(法的統治)の基本である。
しかし、これには後日談がある。もし共和政が実現して政府が真に人民の政府となり、法的統治が行き届いたときに、はたしてこれを覆す抵抗権は認められるのか。抵抗とは、法的統治の否定に対する反対を意味する。法的統治が存在するときに、それに抵抗するのは反対に法的統治を否定するのだから認められない。カントはフランス革命後の『人倫の形而上学』(1797)で、共和政の下での抵抗権が自己矛盾に陥ることを指摘し、抵抗権を否定した。
この指摘は、もし政府権力を設立する人民が相互に同等であり、政府と人民がまさに一体としてあるならば、なかなか反論しにくい。もはや抵抗は認められない。しかし、はたして政治的社会はカントが想定するほどに予定調和であろうか。政治的社会において支配者層の意志が人民に反することは共和政の下でさえも、つねに存在しうる。このときに、政府を覆えそうとする運動は、これを抵抗権の現れととらえることは可能であり、認められてよい。法律に違反すれば犯罪として罰せられる。憲法違反の法案を成立させようとして立憲主義に反する政府は、法的統治の前提を否定するかぎり、ロックに立ち返り、やはり人民の抵抗によって断罪されて然るべきであろう。集団的自衛権問題はこのような問題として存在しているのではなかろうか。